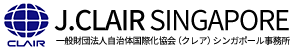世界経済フォーラムが毎年公表している「ジェンダーギャップ指数」は、経済活動や政治への参画度、教育の水準、出生率や健康寿命などから算出されるもので各国における男女格差を測る指数となっています。2016年度、日本が144か国中111位だったのに対し、フィリピンは7位と、アジアの中でもトップの順位となりました。
このように男女格差が小さいフィリピンで取られている政策やそこに住む女性の意識などについて、9月19日~21日の3日間、フィリピンで調査を実施しました。
1 The Philippines Commission on Women
The Philippines Commission on Women(PCW)は1975年に大統領府直属機関として創設されました。フィリピンの政府機関におけるジェンダー政策の中心的な役割を担っており、ジェンダーに関する政策の立案などを行っています。
フィリピンでは各省庁や自治体、国立大学などあらゆる機関で予算の5%以上をジェンダーのためのプログラムやプロジェクトに充てることが法律で定められており、ジェンダー平等の面においてPCWからの承認が下りなければ各省庁や自治体などは予算を執行することが出来なくなっています。
2 Women Involved in Nation Building
Women Involved in Nation Building(WIN)は1988年に設立されたNGO組織です。コミッションメンバーには、元州議会議員や会計士など様々な職業の人がおり、市長や議員などからの相談に応じたり、貧しい女性が職を得るための当面の資金を提供したりするなど、それぞれの人脈や専門知識を使ってジェンダーに関する活動を行っています。
前述のとおり、フィリピンでは予算の5%以上をジェンダーに充てる必要があります。そのため、地方自治体の中には、WINが開催しているジェンダー関連の有料のセミナーに職員を出席させるところもあり、この参加費がWINの運営費にも充てられています。セミナーは、フィリピン国内の各地域で、年2回、地方自治体と連携して開催している700名規模のもので、「災害時の女性の役割」など毎回テーマを設け、州知事や市長などが講演を行ったり、経験の浅い市長が経験豊富な市長から法律の政策立案の方法などを学ぶ場を提供したりしています。
3 フィリピン大学ロスバニョス校
フィリピン大学ロスバニョス校には、2015年にジェンダーセンターが設置されました。センターでは大学の教授や専属の職員が働いています。主に学生や学校職員など、大学関係者を対象としてセクハラや若年者の出産などの相談に応じていますが、その他にも近隣の自治体でジェンダーに関するセミナーを行うなど、大学直轄の機関として教育や調査などを実施しています。
また、この大学では、学生に対してのインタビューも行いました。インタビューした学生の中には、地方出身で実家が貧しいにも関わらず奨学金を得て勉学に励み、将来に対して前向きな話をしていた女性がいました。彼女の「地方にはもっと教育を受けたいという女性は多くいる。しかし教育を受けるためのアクセスがなかった。今は少しずつ情報が入ってくるようになり、夢を持てるようになった。だから将来、私は自分の故郷の人たちにもっと教育を受けられるようにしたい。」と話していた言葉は印象的でした。
フィリピンにも伝統的に男性が一家の長として働き、女性が家族の面倒を見るという風潮がありました。しかし、現在は女性だけでなく男性の意識も変わり、女性が働き活躍することに対して理解を示すようになってきています。現在のようにフィリピンの男女格差が小さくなったのは、一朝一夕にできたものではなく、ジェンダーに関する法律の制定や施行といった行政レベルでの後押しと、NGOなど民間団体による草の根レベルの長期的な活動が実を結んだものであることが今回の調査で分かりました。
なお、今回の調査の内容は、今後クレアレポートとして執筆する予定です。