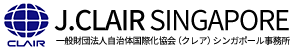1.危機管理会議
11月10日(木)から12日(土)にかけて、シンガポール民間防衛庁(SCDF)の主催により「危機管理会議2016」がシンガポールにおいて開催されました。これは、東京都が実施する多都市間実務的協力事業「危機管理ネットワーク」の一環として各都市行政機関の危機管理専門家が集まり、取組事例の紹介や意見交換を行ったものです。
毎年、当該ネットワーク参加都市が持ち回りで開催しており、今回は14回目となりました(2015年は東京都)。東京都は幹事都市として毎回参加していますが、今回は、シンガポールのほか、ジャカルタ、クアラルンプール、ソウル、ロンドン、台北、および新北が参加しました。
東京都は、被災地復興に向けた取組みとして、被災者生活再建支援システムによる罹災証明の発行や必要な情報を提供できる仕組みと昨今の多様化する救急業務に対して機動的に運用できる救急機動部隊の活動に関して報告するとともに、若い力や語学力を活かしたボランティアの育成の必要性にも触れながら、自助、共助、公助の重要性を説明しました。今回、当事務所は幹事都市である東京都からの依頼に基づきその活動を支援しました。
2.シンガポールにおける危機管理
シンガポールは地勢的に大きな自然災害にほとんど見舞われない国ですが、小さな島国ゆえ人口密度が高く、高層ビルや公団住宅などが密集しているほか、石油化学工場を住宅地の近くに設置せざるをえない状況にあります。そのため、住宅密集地域で火災などが起きると、甚大な被害がもたらされる危険性が高いといえます。また、他の都市に比べて緊急対応に従事する職員が少ないことに加え、任務が困難な上に人材育成に時間がかかるため即時の増員ができないなどの課題を抱えています。このような問題意識の下、危機管理の柱として、①運用上の卓越性、②国民の保護、③コミュニティ対策の3点を掲げています。緊急現場においては、第一発見者が最良の対応ができることから、救急隊が駆けつけるまでの初動の重要性を踏まえた自助、共助を重要視しています。そのために、トレーニングを受けた住民によるチームなどの組織化や第一発見者がすぐに近況を救急隊へ通報できるモバイルアプリシステムの構築を推進しています。事例発表において、システムを駆使したシミュレーショントレーニング環境を取り入れた効果的な人材育成プログラム整備や最新技術を積極的に導入したシステム構築の現状が紹介されました。
3.危機管理分野におけるコミュニティの重要性
今回の会議では、災害発生時の初動対応をいかに迅速に行うかが議論の中心となり、現場に居合わせた住民が協力して初動対応できるようになるために訓練を積み重ね、顔の見える関係を作ることが重要との認識に関する言及が多く見受けられました。特徴的であったのは、各都市の置かれている環境は異なりつつも、自助、共助、公助のコンセプトを各都市が言及していたことです。
危機管理においては、想定しえない、未知の事態にどう対応するかも求められますが、他国の災害経験とその対応策を共有することで、想定しえない事態に対するアプローチや対応できる境界線を広げることができます。今回の危機管理会議で共有された知見を各都市の危機管理対策に還元されることが期待されます。なお、次回は2017年にソウルでの開催が予定されています。